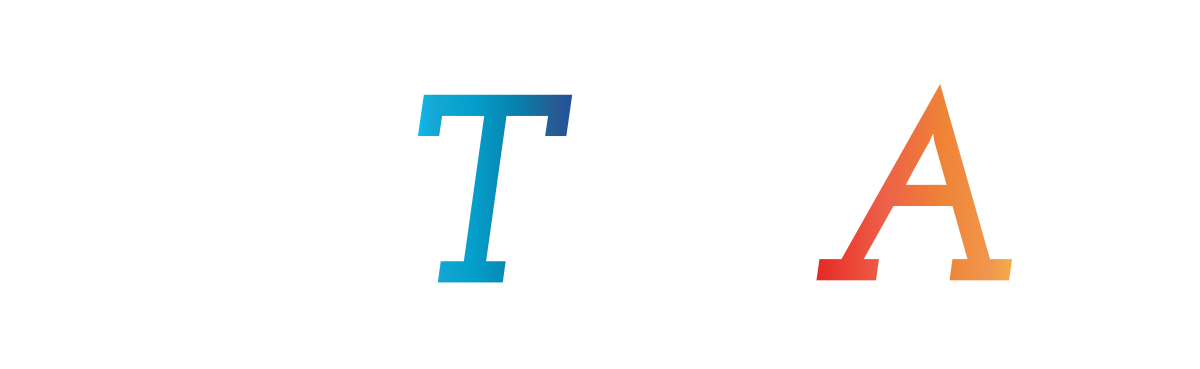『グレイテストショーマン』をついに見た。何か心打たれるものがたくさんある。こういう感覚(つまり、ロックだとかアートだとか)を現実に持ち込むことのリスク(怪訝な顔で「お前の足元をよく見ろよ」と言われる)を多分に承知しつつも、僕はなにか思いに掻き立てられて文章を書いてしまう。批評のことばを僕が放ちきれるわけではない。が、なにかことばに残しておきたい。
最近、考えていることのひとつが「工学に還元しきれない人文的ななにか」についてだ。今の時代は端的に言って工学の時代だと思っている。もちろん、これは主語がとても大きい、だけど、敢えてなにか行動を起こすこと、生きることが世間や他者から「工学的ななにか」に当てはめ込められることを「工学の時代」的なものであるということに止めよう。もう一つ、脚注を入れるなら「工学」はとても役に立つし、重要だ。そうしたもの「敵視」しているわけでは断じてない。なぜなら、世の中はめちゃくちゃ複雑であるからこそ、理論的モデルを構築しつつアプローチしなければ、「何をなしたのか」も「何を反省すべきなのか」も「何が変わったのか」もよくわからないものに溢れているからだ。このように書くと「世界を細分化して理解すべき」といった価値観との親和性を喚起するわけであるが、そう、僕はなんだかんだ言って「よく調べないと分からないこともたくさんある」と考えていて、だからこそ人間社会を研究的に扱おうと「科学」的であることを否定したいと一概には思わない。
こういった注釈をいちいちしないと、何をどのように読み取られるかわからないというのは面倒だけども、やはり大学院生にもなって、それなりに知識を身に着け思考を練磨させ経験を積む中で「何をどのようにいつどこで誰に向かって語るか」に関するメタ解釈やメタ認知が進んでしまったので、面倒であるけども丁寧に語っていかねばならないという思いが強くなった。面倒だが大事だし、このようなすり合わせはとてもエキサイティングな営みでもある。だからこそ、僕は「研究」という道を一つの指標として選んだ。
しかし、いくら「役に立つ」、「客観的な」ものとしての「工学」や「科学」が大事だと思っていても、それだけでは語りきれないなにかに「人文知」があると思っている。これは信仰(近いといえば近い)ではなく、事実、人文知が語りきれないなにかを見ていく、書き記していく、話し合っていくという意味でも「事実」として役立つものだ。というのも「人間」というのは訳が分からなく、傍目に見て取ると全然理解も共感もできないのだけど、その人や社会文化にまつわるものを読み取っていく中でその「訳のわからなさ」が「訳のある」ものとして落とし込まれるのだ。
例えば、この『グレイテストショーマン』の主人公バーナムは物語の冒頭で父と貧しい状況下の中でいつか夢見る「ショー」を妄想しながら暮らしていることが描かれる。そんな状況を「今」の僕らが見たとき、「そんな”夢”を見ていないで必死に生きろ」と言われえてしまうことだろう。こうこうすれば真っ当な道を生きれるはずだと誰かがささやきかけてくるのだ。その目でその口でその表情や声色で。あるいは”何も語らない”ということさえも。しかし、何をもって「真っ当な道」だと言うのだろうか。お金があることか、自分の親しい身分や価値観の人に囲まれてなんとなく生きることになのか。バーナムのパートナーとして上流階級からサーカスに参画していったフィリップスは、自分を取り巻く社会の息苦しさを覚えつつ、最初は一歩引いていたものの、バーナムと手を取り合う中で「自分の生きる道」を選択し、自覚していった。彼が恋心を抱く劇団員は「黒人」であり、当時の社会的状況においては差別・軽視されていた存在である。しかし、フィリップスはそんな「目」に縛られつつも、劇団員とともに日々を生きる中で新しいまなざしをはっきりと得ていくようになった。
上記のことは「今」、つまり現代社会に生きる僕らにとっては、ある意味でありきたりな物語のひとつで、そういうことは「物語」の中でのことで、「現実」は甘くなく、着々と生きていくしかない側面もたぶんにある、という解釈も十分に可能である。けれど、むしろバーナムにとって、あるいはフィリップスにとっては、それは「自らの生きる道筋を誰かの胸に委ねる」もので、自由を奪うものに等しいと言えるだろう。この映画はそんな人間の「自由」をかけた「人間讃歌」の物語なのだ。そこには、批評家(ジャーナリスト)もいて、ショーマン(ペテン師)や泥棒がいて、上流階級がいて、一方で見世物に怒ったり嫌気がさしたりする人( おそらく世界恐慌の中での労働者階級の鬱憤として演出されたものだろう)もいて、一方でそんな見世物にも「非日常」を想像する力に勇気を貰える人もいるのだ。たくさんの人がいるし、だからこそぶつかり合い、時に手を取り合っていく。「人間讃歌」としての力強さがストレートに描かれた作品なのだと感じた。
たびたび出てくる「芸術」や「家族」といったキー概念を丹念に洗い出すほどの余裕も専門性もないが、この作品に描かれる「意外性」や「偶然性」といったものはまさしく「人文知」だからこそ語りうるものの一つだろう。バーナムが少年時に露頭でパンをくすねるとき、成功を得たあとにも火事で全財産を失うとき、生きてる中で「今その瞬間だけ」を見れば語りえないものがこの作品を通して異なる意味として「希望」や「喜び」、そして当然また「悲しみ」を語ることで、「今ここ」から「今ここ」を越えていく何かを放つことができるのだ。
もちろん、それはなにか政治や社会をはじめとした制度や社会問題を具体的に変えうるものとは言えないかもしれない。しかし、だからといって「変わらない」とはわけが違うのだ。なぜならこの作品は「工学」を描くために作られたものではない。一方で「人間」が描く作品として喜怒哀楽が詰め込まれてもいる。こうしたメタメッセージの積み重ねが少しずつ、選択を変え、生き方を変え、政治を変え、世界を変えるなにかにつながっていくとしたら、それは単なる「夢想」なのだろうか?
どんなメタメッセージを受け取るのかは人それぞれでも、解釈に「正しいものなんてない」ということはないということを頭に入れつつ、日常の中の非日常を、非日常の中の日常を、まじめにふまじめにことばとしてだけでなく行為としてもふるまって変わりゆく何かがあると僕は信じている。それがどんな意味をもたらすか。改めて味わっていきたいと思わせてくれた作品のひとつになりそうだ。