
Profile
名前:青山俊之 | Toshiyuki Aoyama
出身:千葉県茂原市
思わず「自分ごと化」してしまうような問いを通じて、「驚き」を紡ぐ関係を広げたい。
ラーメンとWebを嗜む物書き、青山俊之です。このメディア『T LAB』では、冒頭の想いを込めて、ゆるりと知的で面白い文章をお届けしています。なぜ「自分ごと化」や「驚き」を大切にしているのか。その原点は、大学院で博士号を取得した研究テーマ「日本の自己責任論」にあります。
研究について語っておきながらですが、前もって「研究者になろう」と決めていたタイプではありません(ぶっちゃけ今でも「研究者」のアイデンティティはあまり強くありません)。むしろ、宅浪生活を経て苦労して大学に入学したからか、早いとこ就職してお金を稼ぎたいと思っていたし、就職するなら性分としては「ジャーナリストがいいかも」と考えていました。
大きな転機となったのが、2015年のイスラム国による日本人人質事件だったんです。当初、人質の「自己責任だ」と素朴に考えた自分。しかし、すぐに「そんな簡単な話ではない(そもそもテロ行為やそれが起きた国際関係に歴史もある!)」とその考えに違和感も覚えました。
なぜ自分は、二つの異なる考えを持ったのか? この問いが、ぼくを「日本の自己責任論」という研究の道へと突き動かしてきました。
このように大学生活で出会す出来事に対し「なにかおかしい」と思うことが重なり、気づけば研究の道に進んでいた。それがぼくの実情です。とはいえ、大学入学当初に思い描いていた、ジャーナリズム、そしてアカデミズムの精神を織り交ぜて今も活動しています。
根っこはまじめに生きているつもりですが、基本はマイペース、そして適当で、無責任な人間です。いろんな人が語る「自己責任」に関心を持ったのは、きっと無責任の価値を訴え直したかったからでしょう。
根本的に、責任をとる、いわば「けじめをつける」というのは言うほど簡単ではなく、多少は無責任でいた方がむしろ責任はとりやすい、きっと多くの人が生きやすくなるはずだ、とふまじめにまじめに思っている節があります(たぶんこれは変わらない笑)。
そういうふまじめな性分があってか、現実の生きづらさを少し緩和してくれる、ワクワクする未来や技術に期待させてくれるメディアが基本好きです(趣味はマンガ、アニメ、時々ゲームです!)。最近はむしろネットこそが、生きづらさをもたらす磁場として象徴的な影響を与えていることに、うんざりしないわけではありません(エコーチュンバー、ポストトゥルース云々)。が、やっぱり新しい「驚き」に出会う機会はいいものです。
そんな「驚き」と出会うだけではなく、欲望を引き立て、ヒト・モノ・コトの触媒となるメディアは自分にとって切っても切り離せない存在です。最近は、博士論文の書籍化を進めながら、「次はどんな面白いことができるかな!」と作戦を日夜練っています。
その成果の一つが、ぼくの人生を貫く活動の軸として定めた、冒頭で掲げたこのコンセプトです。
何で:(思わず)「自分ごと化」につながる問い
何を:「驚き」を紡ぐ関係を広げたい
とどのつまり、ここでいう「自分ごと化」というのが(公的に誰もが)語る「自己責任」だけではなく、(私的な個人に)宿る「自己責任」だというのがぼくの基本的な考えです。
大学時代に開設したこの個人ブログをはじめ、Webで学術メディアの開設、インタビュー記事の編集、イベント企画・運営、コンテンツマーケティング、そして研究などなど、実にさまざまなことを半端にやってきましたが、貫くのは何を隠そうこの「自分ごと化につながる問いで知的な『驚き』を広げる」活動です。
現在は個人メディアとして称している本サイトでは、執筆・編集業の傍ら、ゆるりと知的で面白い文章をお届けしたいと思っています。いつか、みなさんの「驚き」と「問い」を聞かせていただけるのを楽しみにしています。ではでは、また別の文章でお会いしましょう。またね!
主な業績
学位論文
- 青山俊之(2024)自己責任ディスコースの言語人類学的研究─中東地域日本人人質事件を題材に─, 筑波大学国際日本研究学位プログラム博士論文
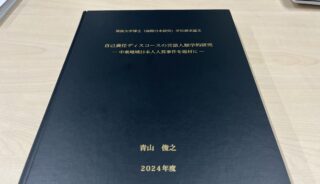 博士論文「自己責任ディスコースの言語人類学的研究」が公開されました。
博士論文「自己責任ディスコースの言語人類学的研究」が公開されました。
学術論文
- 青山俊之(2021)自己責任ディスコースの詩的連鎖―ISIS日本人人質事件におけるブログ記事に着目して―, 社会言語科学 23 (2), p.19-34.
- 青山俊之(2020)自己責任ディスコースのメタ語用論的範疇化によるタイプ分析, 国際日本研究 12, p.121-136.
 5分でわかる拙稿「自己責任ディスコースの詩的連鎖」論文──IS日本人人質事件を題材に
5分でわかる拙稿「自己責任ディスコースの詩的連鎖」論文──IS日本人人質事件を題材に
研究発表
- Aoyama, Toshiyuki. Fractal meanings and cultural logics: Metapragmatics of “jiko-sekinin (self-responsibility)” in Japan, The 18th International Pragmatics Conference, 2023年7月14日.(口頭発表)
- 青山俊之, 「いじり」をめぐるメタコミュニケーション──YouTube動画におけるゲーム実況とコメントを事例に, 社会言語科学会シンポジウム 第3回スチューデント・ワークショップ, 2022年9月3日.(口頭発表)
- 青山俊之, 井出里咲子, ゼミ的コミュニティ形成と責任の再考──言語人類学系ゼミを事例に, 言語文化教育研究学会 第8回年次大会, 2022年3月6日.(口頭発表)
- 青山俊之, 「自己責任論」の記号イデオロギーに関する言語人類学的分析──イラク日本人人質事件における初期報道に着目して, マス・コミュニケーション学会 2021年秋季大会, 2021年11月.(口頭発表)
- 青山俊之, Twitterを媒介に「感染」するイデオロギー──「過労死は自己責任」ディスコースを事例に, 社会言語科学会シンポジウム 第1回スチューデント・ワークショップ「ディスコースから捉える『自己の位置づけ』-4つのフィールドから-」, 桜美林大学, 2019年9月.(口頭発表)
- 青山俊之, サイエンスコミュニケーションと公共性──アカデミックディスコース実践としての『Share Study』,日本サイエンスコミュニケーション協会2019年度第1回研究発表会, 筑波大学, 2019年7月.(口頭発表)
- 青山俊之,文系学部廃止論争とはなんだったのか──批判的談話研究を用いた分析, 第42回社会言語科学会, 広島大学, 2018年9月.(ポスター発表)

