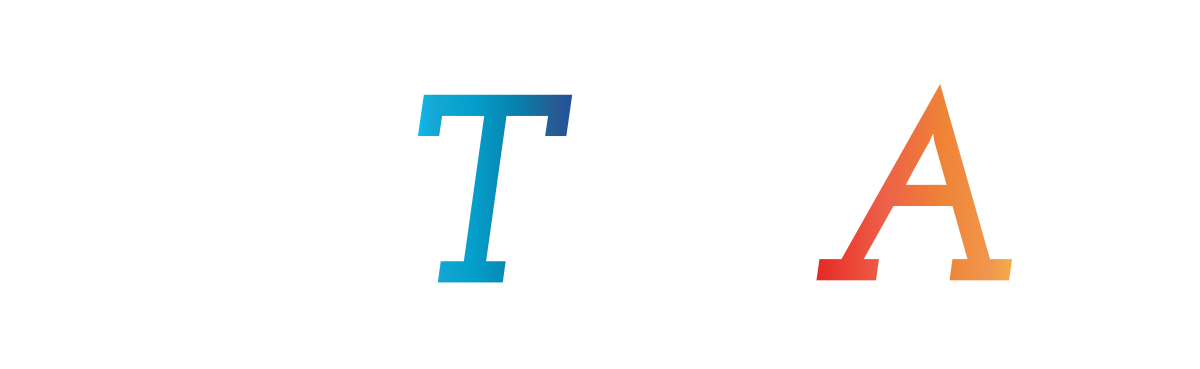ぼくが言語人類学を中心とした研究キャリアをスタートしたのは、井出里咲子先生との出会いがきっかけだった。言語人類学が扱う領域はとても広い。ぼくが扱ったのはそのほんの一部で、専門特化した勉学に励んできたわけでもない。ある意味、「素人」だ。
だが、素人だからこそ言語人類学をぐるぐるとさまざまな視点で見てこれたと思う。この記事では、次の4つの観点から言語人類学とはどのような学問なのかを紹介する。
- 意味:生きたことばを探究する
- 歴史:進化論から相対論的思考へ
- 科学:記号のパターンを発見する
- 総合:学際的な経験的研究
1. 意味──生きたことばを探究する
言語人類学とは、ことばを中心とした文化人類学とも言われ、主にアメリカで発達してきた学問分野だ。言語人類学は、変わりゆくことばの「意味」を徹底して探究する点に特徴がある。
たとえば、日常会話では文法も意味もそこまで意識していないのが大半だが、それでもことばのやりとりは続けられる。文法にも表現にも確かに「言い間違い」はあるが、「いつ、どこで、誰に対して、どのように、なにを言うのか」といった状況によってどこまで気にするかは変わる。これが「普通の人」の感覚だろう。
だが、欧米由来の多くの言語学では人々が日常的に使いこなすことばに必ずしも迫ろうとはしてこなかった。というのも、動物のなかでも人間が唯一、文法を使いこなせることはなぜかを探究の中心に据えてきたためである。
これまでの言語学が同一・同質的な「言語能力(competence; コンピテンス)」を探究してきたのに対し、言語人類学ではことばが用いられる状況・文脈を含めた「コミュニカティブ・コンピテンス」を探究してきた。こうした言語能力観が、コミュニケーションを介して生まれる文法的・記号的なことばの「意味」を探究する言語人類学の大きな特徴である。
※ 「ことばは生き物(living language)」は言語人類学においてひとつのクリシェとなっているが、この考えに固執しない方がいいとも最近は考えている。
2. 歴史──進化論から相対論的思考へ
人類学の潮流の源は主にヨーロッパにある。19世紀当時に盛んだった歴史言語学・比較言語学のなかでは、「ラテン語」を最終体系として考え、進化論に影響を受けた言語観が覇権的だった。
一方、アメリカでは19世紀後半に「明白なる使命(Manifest Destiny)」の標語のもとに西方へと領土を拡大するなか、各地の先住民の言語記述が行われていた。この調査でも、集団間の優劣でその価値を測る進化論的思考から自由ではなかった。

こうした潮流に一石を投じたのがフランツ・ボアズ(1858-1942)であった。ボアズは、これまでの研究者が名詞などの収集と分類に専念していたのに対し、文法こそが人間の習慣的な「思考への窓」だとして研究を行った。そして、ボアズの経験的調査により見出された民族的な文法体系は、彼らが決して劣った民族ではないことを示すものだった。ボアズの多様な生きたことばの姿を捉える相対的な視点は、文化相対主義という人類学的基礎を築いたとされ、ボアズは人類学の父とも呼ばれる。
ボアズが切り開いた相対論的思考は、その後も弟子のサピアやさらにその弟子のウォーフらの研究に引き継がれていく。文化人類学者のマリノフスキーや言語人類学者のデル・ハイムズらが開いた「他者」を記述する研究にも言語相対論の考えは継承されている。
3. 科学──記号のパターンを発見する
進化論をはじめとした他者表象の問題は、現代の人類学でも絶えず問われる。文化人類学では、1980年代以降に研究活動に潜む政治性を問題視する「文化を書く批判(Writing Culture Shock)」が展開され、特定の人々を外部の人類学者が「民族誌」として記述すること自体が問い質されてきた。言語人類学でも他者表象の問題は無縁ではなく、一人間としての葛藤や社会的な非対称性を引き受けたり、より精緻な分析枠組みを構築したりして研究が行われている。
分析で言語人類学が特に着目するのが、言語・コミュニケーション上に表れる「型(パターン)」である。ここでいう型とは、言語的な文法構造(母音・子音、「です・だ」の形態など)に観察される「規則性」から、あいづち・間・引用・目線といったやりとりにゆるやかに観察可能な「まとまり」まで含まれる。そのため、それらの「型」をどう分析するかを枠づける分析概念や着眼点それ自体が、理論的・方法論的な問題となる(型を分析する中心が詩的機能の発想である)。
まとめると、対象の「記述」、分析で着目する「規則性」、それらを見出す「手法」が言語人類学はとにかく細かい。言語人類学では、ほかの人類学的研究のなかでも細やかな点に配慮・着目して、他者を記述する傾向にある。
4. 総合──学際的な経験的研究
言語人類学は、「意味」の探究を中心に、歴史的な相対性から科学的な規則性まで包括して扱う。そのため、言語人類学は、あらゆることばと社会文化の関係を研究する、という大きな野望を持った学問と言えるかもしれない。
言語人類学のなかでも特に壮大な研究射程を持つのが、社会記号論系言語人類学と呼ばれる一学派である。社会記号論系言語人類学はシカゴで発達したパース記号論系譜の言語理論を中心に、あらゆるヒト・コト・モノを記号過程として捉え、「全体性、再帰性、批判、歴史」を重視する点に特徴がある。別の言い方でそれをまとめると、社会記号論では、自然(科学・形式・法則)と文化(人間・解釈・実践)を包括して扱うとも明言されている。

このように言語人類学とひとえに言っても、一枚岩ではない。ただ、私見では、言語人類学は、相対性・規則性を重視する総合的な経験的研究だとぼくは考えている。つまり、あくまで人々や世界が体験する出来事を中心にした学問が言語人類学である。逆に言えば、経験に還元できない、記憶や情報に関する問題系は焦点化されていない。
※ これだけだとなにを問題視しているかわかりにくいと思うが、次の「言語人類学は、トランプ現象をいかに『解釈』し、語り直すのか」と関連する論点に少し触れるだけにとどめたい。
現代社会の論点と経験的研究だけに陥る問題について簡単に触れる。まず、言語人類学をおさらいとすると、この学問ではあらゆるコミュニケーション過程を調査・分析するため、公共的な現象から私的なものまで幅広く扱う。だが、情報社会ではまさに経験に還元できない、公的/私的領域が入り組んだ問題が頻発している。
たとえば、昨今の日本と韓国の対立、あるいはトランプ現象をはじめとしたフェイクニュース、あるいはロシアとウクライナの歴史と政治の認識が絡んだ問題を想像してもらいたい。「事実」だけではなく、ここで生じている「解釈」の問題、そしてこれらがメディアを介してさらなる議論を巻き起こしているのが情報社会の論点としては無視できる類のものではない。これらの問題は、「事実」たる経験的な証拠に還元できない。むしろ、あやふやで、確かめることができない記憶やトラウマに関わる問題であり、いわば「劣位」や「敗者」を経験することにより人間が抱えてしまう無意識の問題とも言い換えられる。この現代社会で頻出する記憶が絡む政治的・社会的な問題は、古臭くも新しい「人間とはなにか」という問いを投げかけている。記憶や情報は、人々・社会の経験を調査するだけでは見出せず、それこそ新たな「解釈」の枠組みを必要とする。
では、その「解釈」とはなにをどう考えるべきものなのだろうか。いとも簡単に変わりゆく「解釈」を踏まえてどう語るべきなのだろうか。これらの問いは、情報社会のコミュニケーション現象を考える上で避けて通れない論点だというのがぼくの考えだ。
言語人類学を学ぶおすすめ書籍
言語人類学を学ぶ最初の取っ掛かりになる入門書をふたつあげたい。ひとつ目が、『言語人類学への招待──ディスコースから文化を読む』(2019年、ひつじ書房)だ。この本では、本記事で紹介した古典的な内容はもちろん、著名な研究事例から現代的なメディアを対象とした研究まで紹介されている。三名の著者による具体的な研究事例やそれを実施する上でのエスノグラフィックな体験を踏まえた内容も盛り込まれており、情報としてだけではなく、研究者の体験も垣間見えるおすすめ書籍だ。
ふたつ目に紹介するのが『コミュニケーション論のまなざし』(2012年、三元社)だ。社会記号論系言語人類学を基点に、言語学からコミュニケーション論に至るまでの理論的枠組みを学部1・2年生向けに解説している。一説によると、社会記号論系言語人類学はこれ以上わかりやすくならない。言語学・コミュニケーション論を俯瞰して知ることができ、研究の営みとして「学問とはなにか」ということも問いかける良著だとぼくは思う。
問い──情報社会における言語人類学的研究とは
言語人類学を突き詰めていくと、経験的研究のなかでも優れたまなざしを持っていると感じる。あまり知られていないことで議論が深まらず、もったいなく思うこともこれまで多かった(だからネットで解説記事を書いている)。また、言語人類学的研究の射程は幅広いながらも、実直な仕事を残せるタイプの分野だと思う。
現代は、SNS、動画コンテンツ、生成AIをはじめとしたサービスが日常に浸透し、情報が爆発的に増殖している。そうしたなか、研究キャリアのはじめに言語人類学に触れていた者として、実直な研究をやってきたことには安心感があったし、価値もあると思ってきた。それはいまも変わらない。
ただ、徹底的に「経験」を研究する言語人類学は、人々が生きる日常に目を向けてきたものの、いまや人々を覆う情報環境にはほとんど目を向けられていないとも思う。ここまで情報が拡散するなか、経験を細かく見るだけでは多くの人に価値を感じてもらいにくいだろう。
もし言語人類学が、あらゆる記号を読み解くのであれば、すでに「情報とはなにか」を真剣に考えるフェーズに入っているはずだ。ぼくがこの思考にいたったのは2023年ごろからで、まだ考えをまとめきれていない。ただ、情報は経験に収まりきらないということは言える。表象を問題視することが言語人類学の出発点でもあったが、あらためて情報から表象を問い直す必要があるのかもしれない。