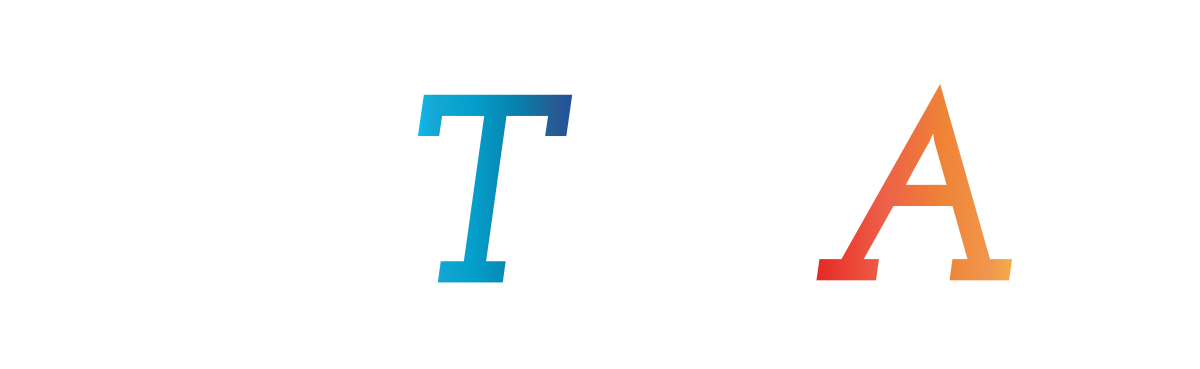コロナ禍がぼくらの日常生活を変えるなか、当たり前にあった日常のコミュニケーションも変わった。特に意識されたのが雑談であろう。コロナ禍では他者とのコミュニケーションがオンラインで代替えされるようになった。もちろん、オンラインでも雑談はできる。けれども、ことばを紡ぐための資源―顔の表情、テーブルの道具、第三者の介入など―が限られている。総じて、オンラインコミュニケーションでは現実世界における身体性が大きく制限される。言い換えれば、コミュニケーションを交わす際に共有する場所性が限られる。「空気を読む」ことはネガティブに語られるけども、コロナ禍の変化は人々が同じ「空気に触れる」ことで生じる雑談のポジティブな価値を思い起こさせた。
雑談は楽しい。とりとめない会話は、その内容はなくたってただことばを紡ぐだけでもたらす元気がある。雑談は難しい。明確に伝えたいメッセージを言い放ったり、思ったことを言ったりすればいいわけではないからだ。雑談はややこしい。とりとめない井戸端会議がいつのまにか誰かのゴシップに変わり、楽しかったはずの冗談がいじりへと展開する。
なぜ人は雑談を求めるのか。どのように雑談は語られているのか。雑談は本当に無駄な営みなのか。雑談はどのように人々がコミュニケーションに向き合う姿勢を映し出すのか。雑談をこのように問うことにはそもそもどのような意味があるのか。
雑談には人を動かす力がある。だとすれば、そこで発揮されることばの力を考えることで、雑談から人間と社会を変えうる道筋が見出せるかもしれない。
本記事では、雑談の多面性に着目しながらその力学を考察する糸口を整えたい。特に、「雑談」という文字記号は二つの読みと意味を持つことに着目する。そのひとつが、とりとめのない会話を指す「ざつだん」であり、もうひとつが、文化芸能の秘訣や苦心などについての会話を指す「ぞうたん」である。雑談(ざつだん)と雑談(ぞうたん)の二面性は、会話と文芸の面白さに加え、それらが交叉する歴史文化的な「型(パターン)」を教えてくれるはずだ。一見、とりとめのない雑談にはどのような型が見出せるのか。いくつかの例を挙げたい。
雑談(ざつだん)とはなにか──フレーム、スタンス、日常儀礼
雑談とはなにか。先ほど、とりとめのない会話と言及したが、本当に雑談はとりとめのない会話だけなのか。たとえば、雑談中に起きるいじりや冗談はエスカレートするといじめにも匹敵する行為になるかもしれない。これらの行為に明確な境界線をつけることは難しい。語り手がどんなに冗談やいじりのつもりであっても、それはその文脈や対人関係によって第三者に「いじめ」だと解釈されえる。ここでいう解釈を枠づける文脈はフレームと呼ばれ、その不定型だけども型をつくるフレームをどう考えるかは意外に難しい。ぼくら人間はこうしたフレームの変化を無意識的に行なっていることが多い。そのように考えると、雑談はむしろキメラ的な性質を持つ大変やっかいなコミュニケーションだと言えるだろう。
フレームは言い換えれば、共通する解釈ゲームのルールのようなものだ。ぼくら人間は日常生活を送りながら、家庭で、学校で、職場で、駅前で、ショッピングモールで、パソコンのインターフェース上で雑談し、それぞれの場に応じたルールを身につけていく。したがって、雑談にはその社会文化で身につける規範的なスタンスが刻まれている。その典型があいさつで、これは日常儀礼とも言われる。儀礼は、「聖なる行為」とも呼ばれ、その形式的・反復的な行為は、それを共有する集団的な規範をつくりだす。あいさつができない人間は、所属するグループからの逸脱を示唆する。だとすれば、どうあいさつが言語化され、行為としてなされるのかを捉えることで、その秩序−逸脱の関係から社会文化的な規範を考えることができる。
雑談の対義語は「正談」だが、雑談はむしろ正談以上に日常に遍在し、正談のなかに雑談が、雑談から正談へと変貌してしまうやっかいなものだ。こうした雑談、あるいはゴシップをめぐる社会規範はぼくが研究する自己責任論とも実はかなり関係している(別記事準備中)。
雑談(ぞうたん)とはなにか──聞書、芸談、対談
一方、鎌倉時代初期から雑談と書いて「ぞうたん」と言われていたのがいわゆる芸談だそうだ。文化芸能の秘訣や苦心である雑談(ぞうたん)≒芸談が、その内容を書き留められると「聞書(ききがき)」とも呼ばれる。そのため、雑談(ぞうたん)は芸能の型や境地の構造や条件を明らかにするものでもあった。日本の文化芸能はこの「雑談≒聞書≒芸談」として部分的に継承されてきたと言えるだろう。
雑談≒聞書≒芸談を取り上げるなかでぼくが念頭に置いているのは、ぼくが所属するゲンロンの取り組み、特にゲンロンカフェとシラスにおける雑談/対談芸である。そこで登壇者と観客の間を取り持つものは、おそらく雑談/対談芸による力である。ここでは、どのように雑談がなされ、どのような対談が文化的な芸能として提示されてきたのか。登壇者と観客が交叉する雑談からどのような可能性が見出せるのか。その雑談/対談芸の聞書がいずれにせよ必要だとぼくは思うのだ。
だが、よく考えてみると、必ずしもここでいう雑談≒聞書は実際に為される芸能活動そのものや能力ではない。ある意味で、そうした本質的なものからすると余計なものかもしれない。ただのレプリカでしかないのかもしれない。
雑談も雑談(ぞうたん)も余計なものとして語られてきた。しかしながら、おそらくそれは単純に必要のないものではなく、「なにか」の意味を付け加えてきたものだった。ぼくが考えたいのはその余計な「なにか」の可能性である。
おわりに
思えば、コロナ禍は余計なものを削ぐことや遠ざかることが大なり小なり称揚されてきた。いや、そうではないという人も、余計なことをしないように無意識的に振る舞っていたのではないか。けれど、抑圧された無意識はどこかで発散する。たとえ個人がどんなに我慢強くとも、社会の集団的な蠢きが爆発的な力能を発揮することは、ネット社会を歩く者なら誰もが知るところだろう。
おそらく雑談はそうした抑圧や葛藤によって溜まったエネルギーをガス抜きするような効果もあるはずだ。その意味で、雑談はまったくもって「雑」ではない力が働き、かつ日常的に親しんだなにかがなにかに変わりうる不気味なものでもある。こんな曖昧模糊とした現象にどう向き合えばいいのか。まだはっきりとした答えがあるわけではないし、おそらく答えられない。だからこそ、ぼくは多層的でキメラ的な雑談から問いとその応答を捻り出してみたい。無駄だけど無駄ではない雑談の力能を味わいつつも見極めること。雑談にはこのようなアクロバティックな可能性がある。