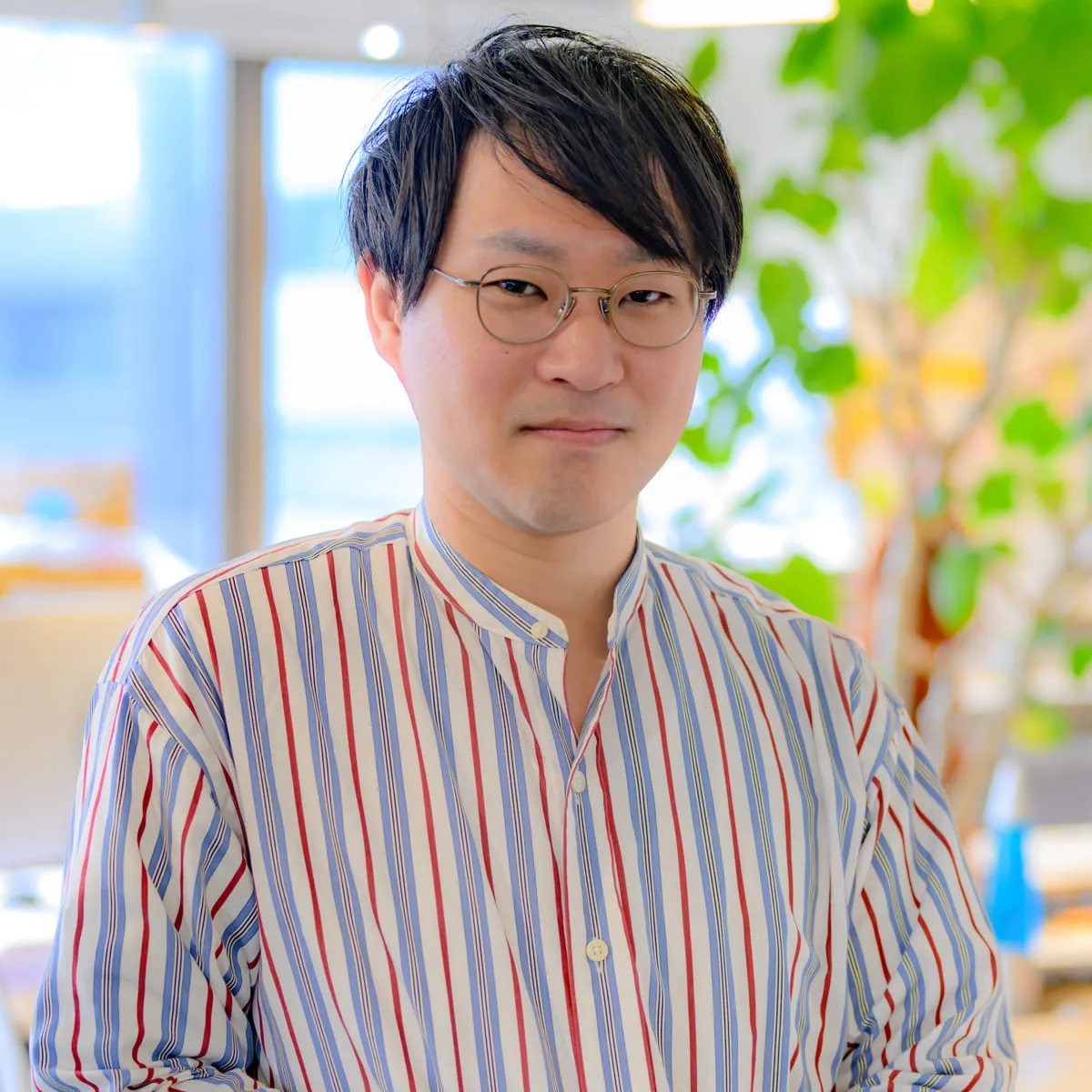参政党が提出し、自民党や日本維新の会も同調する動きを見せる「日の丸損壊罪(日本国国章損壊罪)」法案が、議論を呼んでいる。この法案のミソは、「日本を侮辱する目的」で国旗を傷つけたり汚したりした場合に、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すという内容だ。
ぼくの考えは、「国旗損壊という行為を、それ自体で罰するべきではない」である。もし他人の所有物(市役所の旗など)を壊せば、既存の「器物損壊罪」で対処される。そうした具体的な法益侵害がない(例:自己所有の国旗を燃やす)にもかかわらず、単に「不快だ」、「侮辱的だ」という理由だけで刑罰を科すことは、憲法が保障する「表現の自由」を侵害するもので、そう簡単には許容されないはずだ。
一方、長年、日本の自己責任論争から「保守」と「リベラル」の対立を研究してきた自分からすると、この論争は法的な「正しさ」を主張するだけで収まるものではない。ロジックの応酬でも、感情的な罰則強化でもなく、この論争の背後にあるそれぞれの「動機」や「痛み」を読み解かなければ、議論は平行線をたどるだけだと感じている。
はじめに──「日の丸損壊罪」法案についての論争
この法案をめぐる議論は、典型的な論理と感情の対立を呈している。
反対派は、弁護士ドットコムの記事にもあるように、「表現の自由」の侵害や「立法趣旨」の非論理性を指摘する。対して賛成派は、ニュースのコメント欄などで「国の象徴であり、国民の誇りと信義が込められている」、「侮辱されたとはっきりと受け取る」と強い反発も起きている。
この議論は憲法の表現の自由にもかかわり、慎重な精査が必要なものだろう。しかし、賛成派の声は、必ずしも法的な整合性を求めているものではない。その根底にあるのは、「国の象徴=自分の尊厳」が傷つけられることへの素直な「痛み」であり、「侮辱された」という感情である。この「痛み」を無視して、法的な「正しさ」だけをぶつけても、対話は成立しないだろう。
対立の「なぜ」を想像する──“痛み”の源泉はどこか
では、その「痛み」とはなんなのだろうか。法的ロジックだけでなく、その背後にある「動機」にぼくがこだわるのは、この「痛み」の正体にこそ、対立をほどく鍵が隠されていると考えるからである。
ここで一度、こんな想像に付き合ってほしい。
なぜ「賛成派」は国旗に「尊厳」を重ねるのか
もしあなたが、真面目に働き、ルールを守ってきたにもかかわらず、給料は上がらず、社会的な立場も報われないと感じているとしたら。かつて世界を席巻した日本の産業が、今や他国に追い抜かれていくニュースを日々目にするとしたら。
それは、抽象的な経済の低迷ではなく、「自分の(あるいは親世代の)がんばりが正当に評価されない」という、非常にパーソナルな喪失感や苦しみとして感じられるだろう。
会社や地域共同体といった、かつて自分を支えてくれた「所属先」が揺らぐ中で、「日本(国民であること)」という最後の、そして最も大きな所属先にアイデンティティの拠り所を求めるのは、感情の自然な行き先なのかもしれない──
その時、国旗(日の丸)は、単なる「布」や「国のシンボル」ではなくなる。それは、自分が所属する共同体の尊厳の象徴であり、自分が失いかけている「誇り」そのものと一体化する。
だからこそ、それが燃やされたり、汚されたりする行為は、法的な「表現の自由」の問題以前に、自分の尊厳そのものが踏みにじられる「痛み」として体感される。
なぜ「反対派」は国旗に「懸念」を抱くのか
一方で、「表現の自由」を主張するリベラル派の懸念にも、異なる種類の「痛み」の記憶があると思う。
それは、歴史の記憶だ。かつてその同じ旗が、「公(オオヤケ)」の名のもとに個人の「私(ワタクシ)」の思想や良心を抑圧し、異論を許さず、人々を戦争へと動員したという歴史的な痛みや恐怖の記憶である。これは日本社会の歴史の話だが、きっとリベラルな思想を重視する人は、さまざまな対人関係(たとえば、疎外感を与えるいじめなど)の中で、抑圧的・権威的な振る舞いに敏感な人も多いのだとぼくは経験則的に思うのだ。
国家が法律(刑罰)という「力」を用いて、シンボルへの敬意を強制しようとするとき、だからこそ「自由が再び奪われるのではないか」という懸念がリベラル派には体感される。
「罰則」が「誇り」を傷つける逆説
両者が異なる「痛み」を抱えている中で、賛成派が処方箋として求める「罰則(=異論の排除)」は、危うい逆説を生む。
刑罰で守らなければ維持できない尊厳とは、裏を返せば「損壊されたら傷つく」と自ら認める「もろい尊厳」である。また、罰で強制される敬意は本心からではなく、監視下でのタテマエの敬意にすぎない。
この問題は、本質的には刑罰による強制だけで考えるべきではない。それは、賛成派が守りたいはずの「国民の誇り」を、むしろ“傷つける”可能性を捨てきれないとぼくは思うからだ。
「公」と「私」のネジレと、空転する「正しさ」
この問題の根源は、長年の自己責任研究から、ぼくは日本社会特有の「公」と「私」の関係性のネジレに行き着くと思っている。そのネジレを見直す問いとなるのが、なぜ賛成派は「公(国旗)」の尊厳を主張しながら、その動機は「私(個人のアイデンティティ)」の痛みにあるのだろうか、だ。
この問いかけの先にこそ、石破前首相が「戦後80年所感」で問題提起した、先の大戦で「なぜ政治システムは機能しなかったのか」という核心点とが重なる。その石破さんなりの答えが、「責任の所在が明らかではない」状況では、人々は「勇ましい声とか、大胆な意見」に引きずられ、「情緒的な、非論理的な結論に導かれやすい」であった。
しかし、この問題の根源をさらに深く掘り下げると、日本社会特有の「公(オオヤケ)」と「私(ワタクシ)」の関係性のネジレに行き着く。その問題を鋭敏に読み解いたのが批評家・加藤典洋である。加藤は、『日本の無思想』において、日本社会にはタテマエとホンネが相互に依存し、他者(いわば世間)の承認によって成り立つ二重のシステムがあると指摘した。
彼の分析で恐ろしいのは、このシステムではタテマエもホンネも、状況に応じて「入れ替え可能」であり、どちらも根源的な「信念(本心)」ではないという点である。だからこそ、たとえばリベラルに多いとされる「正論」やその背後にある「信念」は、その入れ替え可能なニヒリズムの前では雲散霧消してしまうと加藤は論じるのだ。
石破氏が「戦後80年所感」で訴えた、SNS時代において「わかりやすさ」や「行き過ぎ」を防ぐ「中間層」 の必要性や、メディアは「公器」であり、社会の「木鐸」であるとし、さらに政治的な「傾聴」を訴えるのは、失われた「公」を取り戻そうとする啓蒙的な試みだろう。
しかし、彼が直面している困難(=なぜその彼自身の“正論”自体も政治的に通じないのか)とは、「ニヒリズムが蔓延した土壌」そのものが、彼の啓蒙を阻む巨大な壁となっている現実にある。それこそが、ぼくらが「研究/批評」と「実践/仕事」の狭間で問い続け、向き合わなければならない課題でもある。
このすべてをここで解き明かすことはできない。しかし、このネジレの構造こそが、ぼくが研究してきた自己責任論から今回の国旗損壊罪に至るまで、日本社会で「正しさ」をめぐる議論が空転し続ける根本原因だと考えている。
おわりに──落とし所に向かうための「勇気」
週末、ぼくは石破前首相による「戦後80年所感」の動画を見ていた。彼が繰り返し主張していたのが傾聴の重要性であり、エスカレーションする言論の分断を避ける中間層の必要性である。
今回の議論も、それぞれの動機や背景の根底を突き詰めれば、社会の声をいかに聴き、いかに「マージナル(周縁)」な領域への想像力を膨らませられるかという問題にぶち当たる。
必要なのは、賛成派の痛みも、反対派の懸念も、どちらも単純に否定せずに向き合う「苦しみと向き合う勇気」なのだと思う。言うは易く行うは難し、という類のものだが、これこそが、感情的な罰則でもなく、ロジックの切り捨てでもない、真の「落とし所」に向かう道筋だと思うのだ。
11月24日(月・祝)の19時から行うぼくの初LIVE配信「雑談、論壇、直談判! 戦後80年、日本の自己責任論を考える」では、この「公と私のネジレ」や、博士論文のテーマである「自己責任(歴史的・意味的変遷についてはこちらの記事を参照)」と、その書籍化のタイトルに掲げる「聴す責任」についてもみなさんとお話ししたいと思う。無駄な時間にはしません。ぜひ寄ってみてください。