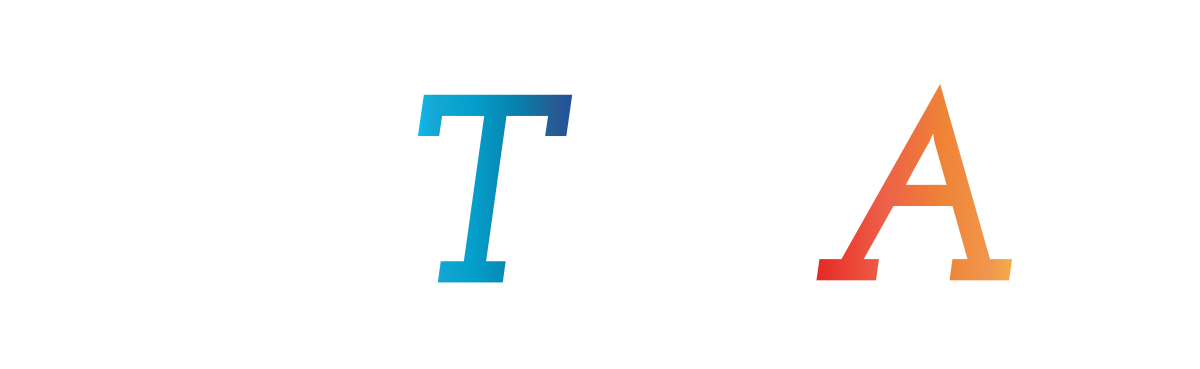グレゴリー・ベイトソン(Gregory Bateson, 1904 – 1980)というアメリカの人類学者がいる。ベイトソンは『精神と自然 生きた世界の認識論』(2022年 [1979年]、岩波書店)という書籍を書いており、ここでいう精神は「人間・文化」、自然は「科学・規則」を指している。ベイトソンがユニークなのは、人類学者として精神と自然の両方を、メタ的に捉える視点や議論を提起した点だ。このベイトソンの議論は21世紀となった今でも参考になるし、あるいは人類学的研究をめぐる表象の危機(ライティングカルチャーショック)以降でも十分に有効だと思う。
人類学的研究における表象の危機と存在論的転回
表象の危機とは、人類学が恣意的に他民族・他文化社会を記述し、説明してきたことに対する人類学内部におけるアイデンティティ・クライシスのことをいう。人類学は、基本的に研究者自らがさまざまな土地柄で暮らす人々のもとに赴き、その生活形態を調査する。現地に赴く調査方法はフィールドワークと呼ばれ、また特に文化人類学では調査にもとづく記述(インタビューや現地資料)とその方法のふたつともエスノグラフィー(民族誌)と呼ぶ。こうした民族誌的研究は、よそから来た人類学者が人々の社会文化を恣意的に、いわば誤って記述してきたことから多くの反省がなされてきた。この表象の危機は1980年代途中から盛んに論じられ、客観性を装う研究者自らの政治的立場や影響力が問題視されてきた。
表象の危機に関する対応はさまざまにある。いわゆる人間中心主義から脱し、非人間のモノ(石といった自然物から建築・機械などの人工物まで)や自然を考える存在論的転回と呼ばれるものもそうだ。存在論的転回以降の人類学が必ずしも人間を置き去りにしているわけではないが、非人間的なモノや自然を中心に考える傾向にあるといっても間違いではないだろう。
※ 正確には、ベイトソン的な発想も存在論的転回の一部論者に援用されているが、ここでは細かい説明は省く。
ベイトソン『精神と自然』の目標と意義
では、ベイトソンはなぜ表象の危機以降、あるいは存在論的転回という流行下においてもユニークなのか? ベイトソンは『精神と自然』の目標や意義をこうまとめている。
本書のプラトニックなテーゼを述べれば、認識論(エピステモロジー)とは、進化も思考も適応も発生も遺伝もすべてテーマとして包み込む不可分に統合されたメタサイエンスである、ということだ。それは最広義の意味合いでのマインドの科学である。
これらの諸現象を並置して検討する──思考と進化との、その両者と発生との類比を考えることが、“エピステモロジー”というサイエンスの探究の方式である。
あるいは、本書の言い方に倣ってこう言ってもよい。──生命過程に関する個々の領域の知見を重ね合わせるところから、エピステモロジーという理解の特典が得られるのだと。
『精神と自然 生きた世界の認識論』(168頁)
要するに、精神を科学的に探究するメタ的な方法は、人間・非人間を含む生命過程に関する知見を比較することにある、とベイトソンは言っている。比較で重要なのは、さまざまな生命過程(カニの構成、音の律動、計算法則、視差による無意識の認知的ズレなど)のパターンを発見することだ。さらに、ベイトソンは前の引用に続けてこうも言っている。
しかし、エピステモロジーとは常に、不可避的に、個人的なものだ。探り針の先端はつねに探究者の心の中にある。「知」knowingの性質(ネイチャー)をたずねる私はそれにどう答えるのか、という問いしか立ちえない。その問いを前に、私は、自分の知の営みが、生物界、生成の世界全体を織りなす広大な知の織り物の一つの小さな織り目だという信念に降伏するばかりである。
『精神と自然 生きた世界の認識論』(168頁)
ベイトソンは人類学者であることを忘れない。つまり、現地で調査し、問いを抱く「わたし」を消さない。言い換えれば、「精神」と「自然」を二項対立的に理解するのではなく、生命過程のパターンを読み解き、そのパターンを探ろうとするわたしという人間であることも忘れない。こうしたベイトソンの姿勢は昨今の人類学的研究では意外に見過ごされがちなようにぼくには見える。
結局のところ、人類学はその名と記述方法・実践を積み重ねた歴史が示すように、わたしと人類を往還して考え続ける学問なのだと思う。ベイトソンは興味深いことに、ぼくら人間が、あるいは研究者が前提にしている枠組みをまとめ、それを知る意義として「前提の組み換えにあたっては、自分たちがいかなる前提を基盤としているかを意識すること、そしてそれを言葉で把握できることが、不可欠とまで言わぬまでも、望ましいのは明らかである」(同書、57頁)と述べている。ベイトソンが言うように、絶対ではないが、ときに自分たちが依拠している前提、つまりイデオロギーを組み替えるにあたっては、それを言葉で把握することは重要な思考のステップだ。「わたしたちは何者なのか」を知ることは、「わたしたちは何者に変われるのか」という可能性を開く、足踏みとなる。