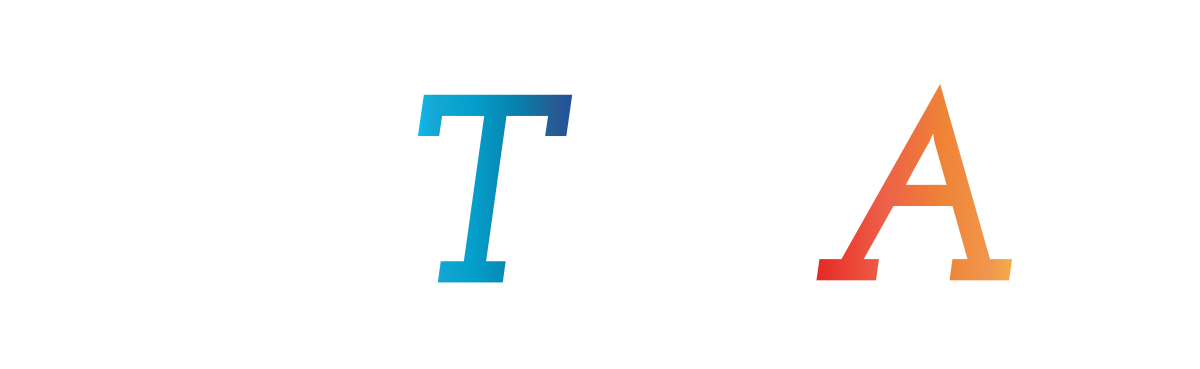日常的にも無意識に使いこなすことばの数々。自分で操っているかのように思えることばは、意外にもそうでもない。ことばには、刻々とことばが生きた場所・時間や人々の声が亡霊のごとく刻まれているからだ。
ことばは変わっていくし、社会も変わる。では、その変遷はどのように捉えられるのか。ことばの使用や解釈に伴うズレに着目する考え方がある。
言語イデオロギー──ことばに関するあらゆる無/意識
冷静に考えて、ぼくたち人間は①規則的な言語構造も②日常的な言語使用も正確にはわからない。誰であろうと、言語を語る人も解釈する人も、なんらかの「歪み」を通してことばを交わしている。この歪み、あるいはズレを言語イデオロギーと呼ぶ。詳細には書かないが、この言語イデオロギーとは言語相対論と呼ばれるもので正確にはちょっと違う。
言語相対論は、俗に言うサピア・ウォーフの仮説における強い言語相対性として論じられてきた歴史がある。強い言語相対性は、言語構造と世界観を直接的に結びつけて理解しようとする傾向にあった。それを象徴する文言が「言語が違えば世界は違って見える」といったものだ。けれども、この理解は正しくない。言語コミュニケーションの捉え方には微細なズレがあり、そのダイナミズムを捉えるのが言語人類学でいう言語イデオロギー論だ。
言語イデオロギー論では、①言語構造、②語用論的無意識、③使用者の言語意識、これら三者間の相関とズレを扱う(小山 2011: 11)。人々のズレがどのように言語構造や言語使用に表れているか、どのように影響を与えているか、どのような意識と無意識の接点があるか。言語イデオロギー論が問うダイナミズムはこれらの問いを指す。
副次的合理化──ことばをめぐるズレを読み解く
ことばにはイデオロギーが伴う。これは避けられない。一方で、言語イデオロギーではある特徴に着目する。それが、意識にのぼりやすい文法や語彙に人々は集中しがちだという点だ。人々が自ら用いている言語やコミュニケーションのあり方を「歪んで」把握してしまうことを副次的合理化という。
たとえば、東京標準語の「なかった」(//(a)nak+at+ta//)の完了・否定表現の音素の配列は意識しにくく、意識しやすいのは([na][kat][ta])という表層的なモーラ(拍)の配列である。ここに関西方言の話者が交わると、「かった」([kat][ta])を、関西方言の否定形である「ん」(a[n])に後続させ、関西方言の「食べなんだ」「行かなんだ」から「食べ(へ)んかった」「行か(へ)んかった」といった表現に変形させることがある。こうして、意識しやすい「かった」が関東・関西で統一される一方、「ない」「ん」の否定形の対比は相対的に意識されやすくなる。標準語である東京のことばを基点に、関西のことばが変容する構図は、「上からの(特に意識に起因する)言語変化」の典型例なのだ(小山 2011: 36)。
記号過程へ
ここではごく一部の例から紹介したもので、言語人類学的な言語イデオロギー論の射程はかなり広い。その射程の広さは、アメリカの哲学者であるC・S・パースによる記号論の影響を大きく受けていることに起因する。では、パースの記号論とはどういったものか? ざっくりいえば、①できる限り観念を明晰にし、②宇宙にまで広がる無限の記号の連鎖、記号過程(semiosis)を捉える哲学だ。
パースの記号論は奥深く、とても難しい。ひとまず、言語人類学的な言語コミュニケーション研究でよく知られるパース記号論の類像性・指標性・象徴性をおさえておこう。
参考
浅井優一(2017)『儀礼のセミオティクス:メラネシア・フィジーにおける神話/詩的テクストの言語人類学的研究』三元社
小山亘(2011)『近代言語イデオロギー論―記号の地政とメタ・コミュニケーションの社会史』三元社
小山亘(2012)『コミュニケーション論のまなざし』三元社